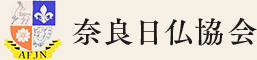第48回 奈良日仏協会シネクラブ例会の案内
48ème séance du ciné-club de l’Association Franco-Japonaise de Nara
聴覚障害を持つ女と監獄から出たばかりの男が形作る奇妙な男女の愛の姿。エマニュエル・ドゥヴォスとヴァンサン・カッセルという二人の名優が演じる新しいフィルム・ノワール。
当日は、ピエール・シルヴェストリさんがパリから来日して解説します。乞うご期待!
◇日時 2018年9月9 日(日) 13:00~17:00 le dimanche 9 septembre
◇会場 奈良市西部公民館4階第2会議室 Nara Seibu Kominkan,
4-kai (3ème étage) salle 2 (près de la gare Kintetsu Gakuenmae)
◇プログラム 『リード・マイ・リップス』(Sur mes lèvres、2001年、119分)
◇参加費 奈良日仏協会会員・学生:無料、一般:300円
gratuit pour membres et étudiants, 300 yens pour non-membre
◇飲み会 例会終了後「味楽座」にて Réunion amicale au restaurant Miraku-za
◇問い合わせ 浅井直子 Nasai206@gmail.com
(スタッフ)
監督 ジャック・オディアール Jacques Audiard
脚本 トニーノ・ブナキスタ Tonino Benacquista
ジャック・オディアール Jacques Audiard
撮影 マチュー・ヴァドゥピエ Mathieu Vadepied
音楽 アレクサンドル・デプラ Alecandre Desplat
編集 ジュリエット・ウェルフラン Juliette Welfling
(キャスト)
ポール ヴァンサン・カッセル Vincent Cassel
カルラ エマニュエル・ドゥヴォス Emmanuelle Devos
マルシャン オリヴィエ・グルメ Olivier Gourmet
マッソン オリヴィエ・ペリエ Olivier Perrier
Coincée, ordinaire à tout point de vue, Carla Behm manque terriblement de charme. Malgré sa surdité, elle est employée depuis quelques années à la Sedim, une société immobilière. Là, elle effectue toutes sortes de tâches ingrates, qui plus est sous les brimades de ses collègues. Une baisse de forme lui donne le droit d’engager un stagiaire comme assistant. C’est ainsi que Paul Angeli, un ex-détenu marqué par les années de prison, entre dans sa petite existence. Sans réelles capacités, Paul a pour lui son étrange beauté. Surtout, il regarde Carla comme un homme regarde une femme. Un amour platonique mais profond naît entre les deux exclus…
Emmanuelle Devos dans l’enfer de la vie de bureau. On ne voit qu’elle, d’abord, en martyre de la photocopieuse, cachant ses deux prothèses auditives. Vu le talent monstre de l’actrice (récompensée d’un césar pour le rôle), cela pourrait faire un film : la secrétaire demi-sourde, bonne à tout faire dans un cabinet de promotion immobilière… Puis elle commande un stagiaire à l’ANPE, comme si elle commandait un fiancé au Père Noël. C’est Vincent Cassel, cheveux graisseux, accent populaire à tailler au couteau. Cela aussi pourrait faire un film : l’employée frustrée et le stagiaire fruste.
Or, le film, c’est encore autre chose : un polar, une histoire de magouilles, de marigot et de magot. Le scénario se révèle plutôt complexe mais le cinéaste veille à ne jamais couper les ponts avec son atout principal, ce drôle de portrait d’une fille trouble et en pleine mutation : on la découvre peu à peu capable de la même cruauté, tenaillée par le même instinct de domination que ceux qui la brimaient. En ce sens, Sur mes lèvres est un film noir original.
(Pierre Silvestri)
目だたず、これといった取り柄もないカルラ・ベームは、魅力的とはとうていいいがたい女性。耳は聴こえないが、数年前から不動産会社セディムに勤めている。会社では、つまらない仕事をし、その上同僚からはいじめを受けている。体調を崩したため、助手として研修生を雇うことになる。刑務所から出たばかりのポール・アンジェリが、彼女のとるに足りない人生にかかわってくるのは、こうしたわけである。実務的な能力はなくとも、ポールには何かしら魅力があった。ポールはカルラを一人の女として見つめる。プラトニックだが深い恋愛感情が、二人の社会のはみ出し者の間に芽生えていく。
エマニュエル・ドゥヴォス(カルラ役)は、オフィスの生き地獄にいる。はじめは、彼女は両耳に補聴器をかくしつけた犠牲的なコピー係りとしか見えない。この女優の途方もない才能が(この役でセザール賞を受賞)、この作品を映画たらしめている。耳の不自由な秘書、不動産販売代理店の何でも屋の小間使い…。つづいて彼女は職業安定所で、まるでサンタクロースに婚約者が欲しいと頼むかのように、研修生の注文をつける。その彼は、油で汚れた髪の毛をして強烈な下町なまりのヴァンサン・カッセル(ポール役)。彼の存在もまたこの作品を映画たらしめている。欲求不満の女性従業員と粗野な男性研修生の物語。
この映画にはさらにまた別の見どころがある。犯罪映画であり、闇取引、悪人たちの溜り場、隠し金の話であること。脚本はやや錯綜しているが、監督のジャック・オディアールは彼の持ち味を失わないようにしている。性格のわかりにくい奇妙な女の肖像と、そのまったき変化である。彼女が自分をいじめた人々と同じ支配の本能にさいなまれながら、同じ残虐性を持つようになることを、観客は徐々に理解する。この点で、映画『リード・マイ・リップス』はいっぷう変わったフィルム・ノワールとなっている。